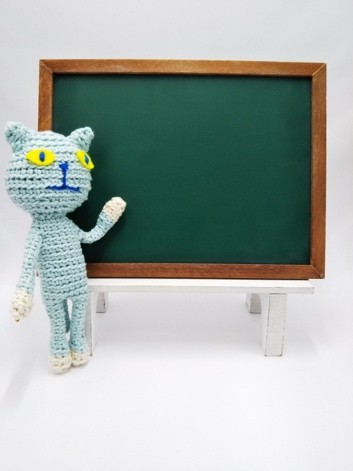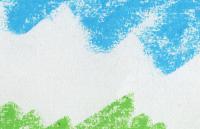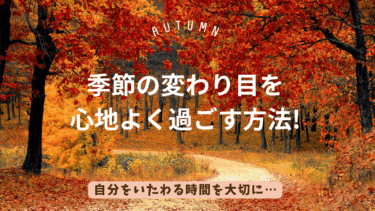みなさん、こんにちは。
ラルゴ神楽坂で支援員・講師をしている井上太一と申します。
簡単に、自己紹介をさせていただきますね。
カウンセリングルームを運営し、かつ心理系の講座を提供する会社に12年勤務した後、フリーの心理カウンセラーとして独立し現在に至ります(それ以前は広報コンサルタントとして16年間を過ごす中で、「企業の危機管理」というテーマを主に扱ってきました)。
心理職に就いておよそ20年。現在は年間で1000件ほどの相談対応をおこなっています。
ラルゴ神楽坂では、およそ5年前から支援員として・また講師として、仕事をしています。
そして、日々の活動の中で、相談者さんに対して提案する機会が多い心理療法が、今日のブログのテーマでもある「認知行動療法」です。
そもそも認知行動療法って?
認知行動療法は、ストレスなどで固まって狭くなってしまった考えや行動を、ご自身の力で柔らかくときほぐし、自由に考えたり行動したりするのをお手伝いする心理療法です。
もともとはアメリカのAaron T Beckという人が、うつ病に対する精神療法として開発したものですが、うつ病以外にも、不安症や強迫症など多岐にわたる疾患に治療効果と再発予防効果があると言われています。
また、現在では、精神科の治療としてだけではなく、法律、教育、ビジネス、スポーツなど、あらゆる領域で認知行動療法の考え方が取り入れられているようです。
そもそも認知行動療法(CBT)ってなに? 国立精神・神経医療研究センターのホームページより
「認知」とは、ざっくり言うと、出来事に対するとらえかたです。「思考の癖」と言い換えても良いように思います。
そもそも人間は、思考の癖だらけです。ぼくも、そして、あなたも。
この癖をすべて修正していくことは、あまりにも膨大な時間と労力を要すると思われるため、現実的とはいえません。ひょっとすると、一生かけても修正しきれないかもしれません。
しかしながら、この思考の癖が非合理的であり、それが元で日常生活や仕事に支障をきたしてしまっている場合、そこだけは修正を試みよう——というのが、認知行動療法のざっくりとした考え方になります。
偏った非合理的な思考や行動を修正する一連の過程で、ご自身を客観視する能力が向上していきます。
ご自身を客観的に見つめることによって、思考や行動を修正し、感情やご病気の症状のより良いコントロール、ストレスのより良いコントロールにつながっていくわけですね。
認知行動療法は応用範囲が広い
ぼくはどちらかというと医療寄りのカウンセリングをおこなう機会が多く、実際に心療内科/精神科でも、カウンセリング業務をおこなっています。
認知行動療法という心理療法は、うつ病、パニック症、強迫性障害、適応障害など、さまざまな病気の治療に有効とされており、したがってぼくも患者さんに対するアプローチとして選択する機会が、しばしばあります。
また、みなさんは「メタ認知能力」というビジネス用語を聞いたことはあるでしょうか?
メタ認知能力とは、自分の認知活動を客観的に把握し、コントロールする能力のことです。
こうした能力はビジネスシーンなどでも強く求められるため、それを高める意図で、企業の研修講師の仕事を請け負う時などは、ご自分を客観視するスキルを上げ、非合理的な思考や行動の癖を修正するような試み
——すなわち認知行動療法に近いアプローチをおこなうこともあります。
ラルゴ神楽坂の講座内でもお伝えしています
本来、この認知行動療法という心理療法は、(治療という目的であれば)相談者さんと心理士の1対1のカウンセリングという構造においておこなわれるものです。
ぼくはラルゴ神楽坂において、ご希望者対しては1対1のカウンセリングをおこなっていますが、多くの利用者さんにこの認知行動療法の考え方だけでも身につけて、プラスに生かしてほしいな…という思いから、(カウンセリングではない)講座の中でもときどき紹介しています。
具体的には、ぼくが担当している『ストレスケア講座』『事例研究講座』という講座の中で扱うことがあります。
とくに『事例研究講座』の中で取り上げることが多いように思います。
この講座は、ぼくが過去に関わり、無事にカウンセリングが終結した事例を(相談者さん個人を特定できないように完全に配慮したうえで)教材として使用しています。教科書から引っ張ってきたのではない、いわば生の教材です。
なぜ事例を用いるかと言いますと、非合理的な思考・行動の癖は、無意識的に出現することが多いため、自分の癖を自覚できていない方が多いのが現実なんですよね。
ところが人間って不思議なもので、自分のことはなかなか洞察できなくても、他者のことならばかなり深い部分まで洞察できるんですよね。
そこで、他者の事例を「入口」とし、講座を受講されるみなさんが自己洞察を深めるというプロセスを体験してもらうことで、自身の中の非合理的な思考や行動の癖に気づき、修正するきっかけにつながれば——という思いと意図が、ぼくとしてはあります。
最後に…就労移行支援事業所を選ぶ際に大切なこと
このブログ記事をご覧いただいている方・ラルゴ神楽坂のホームページにご訪問いただいた方は、おそらく就職をどうしようかとか、就労移行支援事業所選びに迷われている方が少なからずいらっしゃると想像しますため、最後に、就労移行支援事業所を選ぶ際に大切なことを書いておきたいと思います。
就労移行支援事業所は数多くありますが、選び方として大事なのは、ずばり「自分に合っているかどうか」です。
ぼくは年に1000件ほどのカウンセリングをおこなっているのですが、相談者さんの中には、(ラルゴ神楽坂以外の)就労移行支援事業所を利用している方が何人もいらっしゃるのですね。
そうした方々から、
- 利用希望日が満席で(利用を)断られる日がある。
- 自分の状態や事情はあまり考慮されず、事業所のカリキュラムを終えないと具体的な就活ステージに進めないという杓子定規なルールに閉口している。
- 支援員が忙しすぎてろくに対応してもらえず不満だ。
——などといった、他の就労移行支援事業所の様子をお聞きするんです。
ラルゴ神楽坂ではちょっと考えられない情景が語られるため、正直なところびっくりします。
ラルゴ神楽坂では、利用者のお一人おひとりに合わせた、その方に必要な支援プログラムを少人数制のアットホームな環境で提供しており、だからこそ、職場定着率が100%なんだと思います(就職後6か月)。
ラルゴ神楽坂では、無料体験を随時受け付けていますので、どこの就労移行支援事業所を利用するか迷っている方は、ぜひ一度、体験にお越しください。
よろしければ、ぼくの講座ものぞいてみてください😊
![就労移行支援 ラルゴ神楽坂|株式会社 志(こころざし)[東京都新宿区]](https://largo.kokoro34.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2024/09/logo-largo-horizontal.png)